|
【(続)削りぶしの話】
|
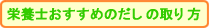 |
| 第6回では「出し汁」のもとになる「削り節」についてのお話をしました。 今回は話をより具体的に進めて、「家庭でできる簡単な出しの取り方」などをお話ししてみたいと思います。 |
| |
|
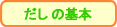 |
今回はお味噌汁を例にとり、「だし」の基本的な分量を少しおさらいしておきましょう。
お味噌汁の1人分の出し汁の量・・・・・カップ1(150cc)
|
原 料
|
水の分量に対しての分量
|
塩分料
|
| 風味調味料(だしの素) |
1g(一般的な商品) |
0.4g |
| だしパック |
商品A10.5g(1袋)=4人分 |
0g |
| 削りぶし |
4.5g(水の分量×3%) |
0g |
| その他 |
煮干し(いりこ)・昆布・椎茸・大豆・干し貝柱等 |
*地域差がありますが、そうめんなどのつけつゆを作るとき、「大豆」でだしを取るところもあるそうです。 |
| |
|
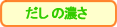 |
| 煮物などに使う場合は上の分量よりも少し薄めにしても大丈夫ですが濃い味付けを好む場合は「醤油・塩」で調整するよりも最初にしっかりとだしをとっておいた方が健康には良いでしょう。 |
| |
|
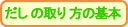 |
| 味噌汁4杯分のだしの取り方です。 |
| |
| かつお又はその他の削りぶしのみの場合 |
| (1) |
お鍋にカップ4杯の水を入れて火にかけて沸騰したら火を弱める。 |
| (2) |
削りぶしを約24g加えて中火でひと煮立ちさせる。
(いわし、さばなどの削りぶしでだしを取るときは、差し水をしながら1〜2分軽く煮出す。) |
| (3) |
火を止めて、鍋の削りぶしが沈むまで待つ。 |
| (4) |
目の細かいざる又はふきんでだしをこすか、上澄みをお玉ですくいとる。
・・・これは「一番だし」を取る方法です。 |
| |
【二番だしを取る方法】
一番だしを取ったかつおをもう一度使います!
(1)鍋に一番だしと同じ分量の水とかつおを入れ、中火で2〜3分煮出す。
(強火で煮るとだしが濁るので気をつけましょう。)
(2)火を止め、一番だしと同じようにする。 |
|
|
| |
| かつお又はその他の削りぶし + 昆布 の場合 |
| (1) |
5センチ四方に切った昆布4枚を用意する。 |
| (2) |
昆布の表面を布巾等で軽く拭いておく。(表面の白い粉は昆布の旨みなので必ずしも、濡れた布巾で拭き取らなくてもよい。)
|
| (3) |
鍋にカップ4杯の水をいれて昆布を入れてしばらく置く。(15〜30分程度) |
| (4) |
(3)を中火にかけ、鍋の底からふつふつと小さな泡が立ち始めたら、昆布を取り除く。 |
| (5) |
後は「削りぶしのみの場合」の(2)〜と同じ。 |
|
|
| |
| 煮干しの場合 |
| (1) |
煮干しの頭と腹わたをとったものを約30g用意する。(細かくさいておくとよくだしがでる。) |
| (2) |
時間があればカップ4杯の水に(1)をいれてしばらくおいておく。(朝、味噌汁を作る時には前の晩につけて冷蔵庫にいれておくと便利) |
| (3) |
(2)を中火にかけて沸騰直前に火を弱めて1〜2分煮出し、その後、こし器等でこすとよい。 |
|
|
| |
